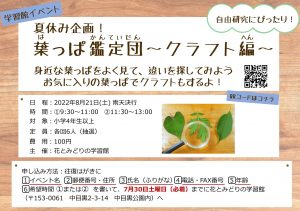みなさんこんにちは!暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。
5・6月の花の時期が過ぎ、夏になり、公園はみどりが濃くなってきました。
そんな時期の公園を歩いていると見つけたのは・・・
まだ小さいですが、オリーブの実

オリーブは5月の下旬から6月の上旬にかけて花を咲かせます。
花が終わり、少しずつ実が大きくなっています。
次にみつけたのは、
小さなカキ。でも形はしっかりあのカキです。

5月頃花を咲かせます。
色が変わるのが楽しみですね。
最後に葉の間に見つけたのは、
まだみどりのクヌギのどんぐり。

どんぐりにもいろいろありますが、
クヌギのどんぐりは2年で大きくなります。
帽子のように見える「殻斗(かくと)」がとても大きく、
実の形が丸いのもクヌギのどんぐりの特徴ですね。
どの実も、風に負けず大きくなってほしいですね。
さて花とみどりの学習館では8月に「夏休み企画!葉っぱ鑑定団~クラフト編~」を開催します。
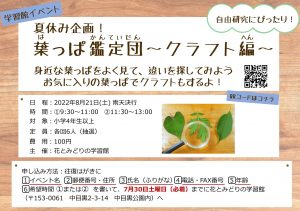
身近な葉っぱをよく見て、違いを探して、まとめることで、
新しい植物の魅力に気付けるかもしれません。
また、お気に入りの葉っぱでリーフタグ作りも行います。

自分でまとめたレポートとリーフタグは持ち帰るので、
自由研究の宿題にもなっちゃいます!
学びとクラフトで1度で2度おいしいイベントです。
ぜひご応募ください!!
詳細はこちら↓
https://www.ces-net.jp/nakameguro-park/?page_id=3962