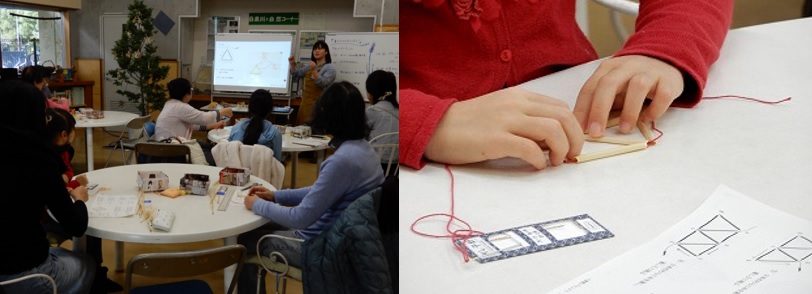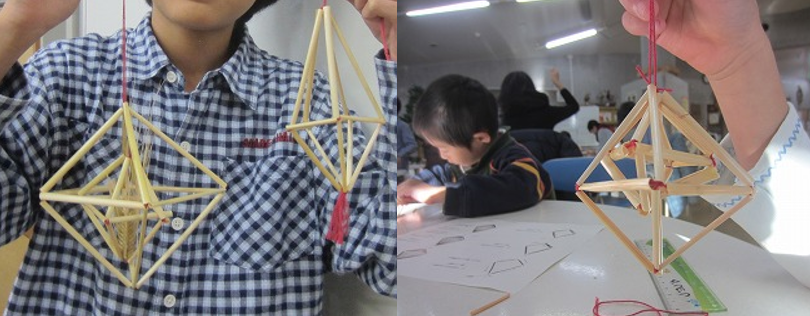花とみどりの学習館では、毎月0の付く10・20・30日を公園作業日としています。
公園作業日では、その時公園で必要な作業に、ボランティアでご参加いただくことができます。
今回は、冬の公園作業日の様子を少しご紹介したいと思います。
この日は、公園の入り口のカナメモチの生垣の剪定を行いました。


剪定は木の生長やバランスを考えながら行う作業なので、思いのほか身体だけではなく頭も使います。

どの枝を伐ってどの枝を残すか迷ったら、いろんな方向から生垣を眺めてみたり、周りの人と相談しながら、和気あいあいと作業を進めていきます。

2時間の作業でこんなにすっきりとしました!
この日はいつもの公園作業日に比べると大掛かりな作業となりましたが、
「今日もよく働いたので、ぐっすり眠れそうだ。」
「冬の間にすっきりと剪定ができてよかったね。」などの感想も挙がっていました。
ご家庭や自分だけではなかなか出来ないような作業を行うことが出来たり、みなさんと一緒に作業をして達成感を味わうことができるのも公園作業日の良いところなのではないかと思います。
「外で身体を動かしたい」「自分にもできるボランティアをしたい」「公園のためにちょっといいことをしたい」など、みなさんが公園作業日に参加する動機も様々です。
ご興味のある方は、ぜひお気軽に公園作業日にご参加下さい。
【~公園作業日ご案内~】
学習館のスタッフと一緒に、草取りや花壇の管理などを行うボランティア活動です。
どなたでもお気軽にご参加いただけます。
その日に集まっていただいた方で、できる作業を行います。
実施日:毎月10・20・30日の10:00~12:00
(休館日と重なる場合、活動はありません)
申し込み:不要・当日花とみどりの学習館窓口でお声がけください
持ち物など:汚れてもよい作業できる格好、軍手など
作業に必要な道具は学習館で貸し出しを行っています。
剪定ばさみなど普段使っているものがある方はお持ち下さい。