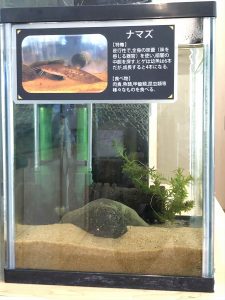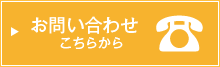今回も野鳥にまつわる話題です。
朝の巡回中、帰真園にて・・・
芝生の上を足早に歩いている野鳥。
普段なら気にも留めないのですが、なんだか見かけない姿のような。
歩き方はハクセキレイに似ているけど姿が全然違うし・・・。

写真を撮って、しばらく図鑑とにらめっこ。
ようやく『タヒバリ』であることに気が付きました。

多摩川河川敷ではよく見かける、そこまで珍しくはない野鳥ですが、
二子玉川公園では、スタッフ初確認!!
随分とのんびり屋さんのようで、
私が写真を撮るのに後をつけても飛んで逃げることもなく、
芝生の上で長いこと過ごしていました。

本当はちょくちょく遊びに来ていたけれど、
私たちが意外と見逃していたのかもしれませんね。
朝の帰真園は人が少なく静かなので、色々な野鳥に出会えます。
特に冬の時期は意外な発見がいっぱい。
ぜひ、野鳥ウォッチングをしに遊びに来てくださいね!!
(なべちゃん)